【第1回】中小企業の事業承継・誰に事業を引き継ぐか

こんにちは、相続専門の税理士法人ともに編集部統括ライターの佐藤です。
この記事では、スムーズな事業承継を望む経営者に向けて、失敗しない事業承継の方法を解説します。全体で11回のシリーズ記事です。
シリーズ最後まで読めば、事業承継の基本的な対策や、法的・制度的な支援策について正しい知識が身につきます。第1回のテーマは、事業継承の概要と、最初に直面する課題「誰に事業を承継するのか」です。
ではまずはじめに「事業承継」の定義について確認しておきましょう。
事業承継とは
事業承継とは、個人または法人で経営する事業を、後継者に引き継ぐことです。
もし経営者が事業の引退にあたり、引き継ぎするつもりがないなら、事業承継について悩む必要はありません。この場合は、利害関係者に迷惑をかけない廃業ロードマップを描いて実行するだけです。
しかし、経営者の引退後も事業を続けたいなら、「事業承継」を考えねばなりません。
中小法人事業承継のポイント
事業承継は法人の規模によって向いたやり方が異なりますが、このシリーズ記事では、特に中小規模の事業を承継するポイントに絞って、お伝えします。
事業承継で引き継がれる要素
はじめに事業承継で承継される内容を確認しましょう。事業承継で承継されるものには、以下の通りプラスの要素とマイナスの要素があります。
事業承継で引き継がれるプラス要素
- 取引先
- 現預金
- 事業用固定資産
- 代表者の地位
事業承継で引き継がれるマイナス要素
- 借入金
- 未払金
全ての要素を順調に引き継ぎ、自らが去った後も会社が従来通りに回るようにすることが、真の「事業承継」です。
しかし同族会社である中小企業では、経営基盤のほとんどが社長個人に帰属していることが多いです。経営基盤の例を挙げてみましょう。
- 取引先との関係構築
- 営業力
- 資金調達力
言うなれば、社長の「人柄」「人徳」「人間的な魅力」によって、経営が成り立っている状態です。
事業承継をするなら、こうした社長個人に帰属する経営基盤も含めて、後継者に引き継ぐ必要があります。
事業承継の3つの課題
実際に「事業承継」を計画するには、次の3つの課題について考えなければなりません。
1つ目は、誰に事業を引き継ぐかという問題。
2つ目は、自社株式をどのように引き継ぐかという問題です。
(※株式の引き継ぎについては第2回目以降の記事で、詳しく解説します)
3つ目は、後継者に対する教育の問題となります。
最初の問題は経営的な(形式的な)事業承継、2番目の問題は所有的な(実質的な)事業承継、3番目の問題は能力的な(人間的な)事業承継とも言い換えられるでしょう。
【事業承継の3つの課題】
- 1.経営的な(形式的な)事業承継=誰に事業を引き継ぐか
- 2.所有的な(実質的な)事業承継=自社株式をどのように引き継ぐか
- 3.能力的な(人間的な)事業承継=後継者に対する教育
最新の事業承継事情
近年の事業承継の流れは、以前とは変わってきています。かつては、中小同族企業を創業したオーナー社長が引退する場合、「子どもに事業を引き継ぐ」と希望する方がほとんどでした。
しかし最近は、以下のような発言が目立ちます。
「自分がしてきた苦労を子どもにまで負わせたくない」
「子どもは既に他の企業に就職して働いている」
「先行き不透明な自分の会社で大変な思いをさせたくない」
自分の子どもには、事業を引き継ぎたくない、と考える方が増えてきたのです。昨今の厳しい経済状況を反映しているのかもしれません。
とはいえ反対に、事業継続を希望する方も、大勢いらっしゃいます。
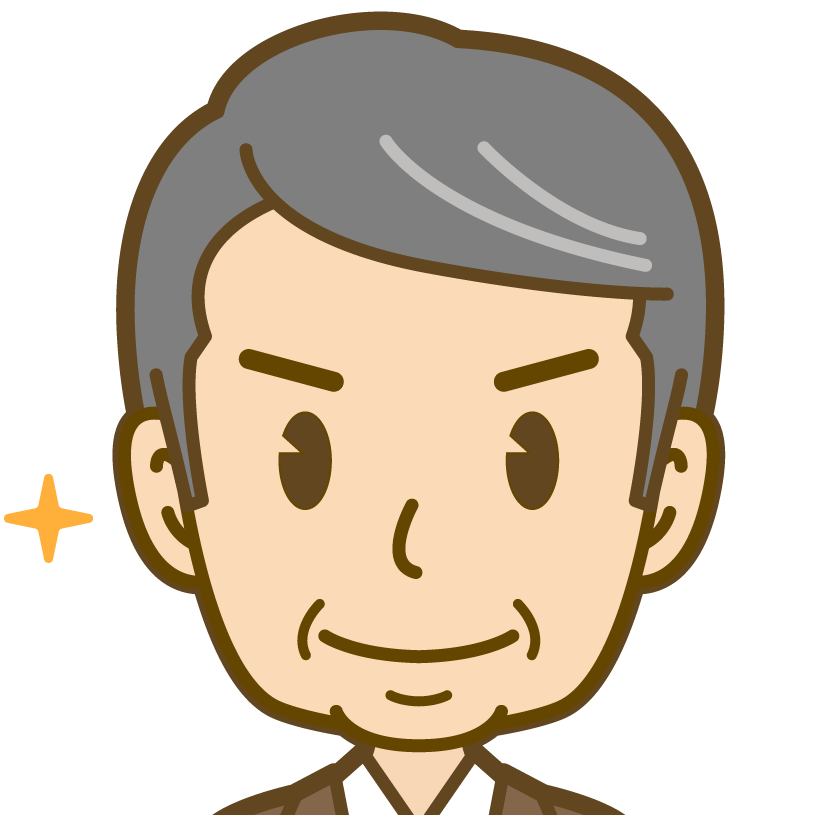
自分が作り、がんばって経営してきた会社を自分の代で終わらせたくない
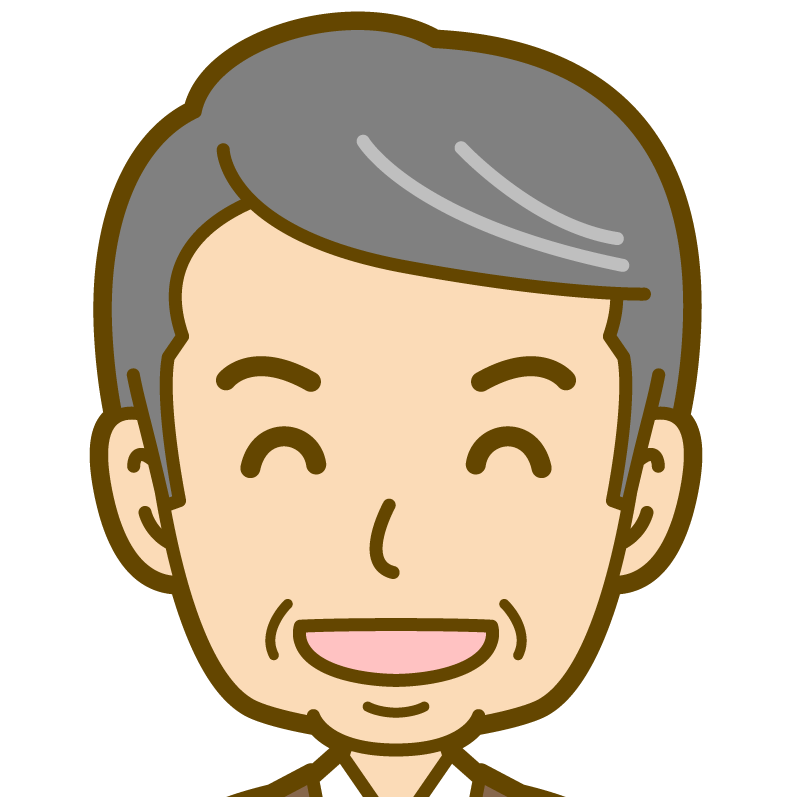
可能なら誰かに継いでほしい
子どもが未熟な場合の経過措置
事業の承継者として自分の子どもを考えているが、後継者としてはまだ未熟で育っていないという状況であれば、打つ手があります。こうしたケースで考えられる措置は以下の2つです。
まず1つは、すぐに子どもには代表権を譲らず、リリーフとして別人が一旦社長を引き継ぐという形。
もう1つは、事業を引き継ぐ会社を探して事業譲渡を行う方法です。いわゆるM&Aです。
M&Aを選択すると、独立した会社という法的な形は無くなります。しかし、事業の実態は継続できます。広い意味で、これも事業承継の1つの形です。
このように、事業承継するなら事前に考えを整理して明確にすべき事項があります。
誰に事業を引き継ぐか
ここであらためて、誰に事業を引き継ぐかを考えてみます。
後継対象は、大きく分ければ「親族」と「親族以外の第三者」に分けられます。M&Aの可能性も含めると、後継対象は「事業譲渡先企業」も加えた3者があります。
【3つの事業承継候補】
- 親族
- 親族以外の第三者
- 事業譲渡先企業
このうち、親族または親族以外の第三者に対して事業を承継するなら、手続きは難しくはありません。この場合は、「代表権の移動」手続きをすればよいです。
代表者交代に関する会社法の規定
代表権の移動についての会社法の規定を解説します。この項は「そういうものか」と流し読みしていただいても構いません。お急ぎの方は、次の「ネックとなるのは後継者選び」へ進んでください。
代表者交代について、会社法では次のように書かれています。
取締役会の権限として、「取締役会設置会社の業務執行の決定」(第1号)と「取締役の職務の執行の監督」(第2号)、「代表取締役の選定及び解職」(第3号)を掲げており、同第3項は「取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。」
出典引用:会社法第362条第2項
要するに「取締役会設置会社における代表取締役の選定は、取締役会における決議事項である」ということです。
もし、会社が取締役会非設置会社であれば、上記条文の適用は受けません。この場合は、会社法第349条第3項の規定により、株主総会が代表取締役選定の権限を持っています。
ただここで、例外があります。
<例外>
取締役会設置会社であっても、定款にその旨の定めがしてある場合には、代表取締役の選定は取締役会ではなく株主総会で行われることになる
実は、「株主総会で代表取締役が決められる」上記規定は、会社法に明確に記載されてはいません。
しかし平成29年2月21日最高裁判所第三小法廷で、会社法の解釈が述べられ、定款に記載がある場合は、この方法で問題ないことが確定しました。
要するに、所定の手続きをとりさえすれば、株主総会で代表取締役を選定してよいと、公式にエビデンスが出たわけです。
【代表取締役の選定に必要な所定の手続き1】
- 取締役非設置会社
- 取締役設置会社で定款に代表取締役は株主総会が選定する旨を定めている会社
→株主総会を開き、代表者を現在の社長から後継者候補に変更する決議を行う
※ただし、代表者は取締役に就任している者に限る
【代表取締役の選定に必要な手続き2】
- 定款に定めが存在しない取締役会設置会社
→取締役会を開き、代表者を現在の社長から後継者候補に変更する決議を行う
※ただし代表者は取締役に就任している者に限る
「事業承継」をお考えの事業主が、ここまで詳しく覚える必要はありません。ただ「法的にはこういうもの」と、何となく頭に入れていただければ大丈夫です。
代表者変更決定後の手続き
法律上は、代表者変更の決議に基づき、代表者変更登記を行います。税務上は、登記が完了次第すみやかに、本店所在地を管轄する税務署や都道府県税事務所等に、代表者変更を届け出なければなりません。
どちらも難しい手続きではありませんので、心配はいりません。
ネックとなるのは後継者選び
真に悩ましいのは、これまで解説した手続きの問題ではなく、誰に事業を引き継がせるか?という後継者選びの問題です。
事業承継がスムーズに進まない事例の多くで、この「後継者選び」問題でつまづいています。
親族以外の第三者への事業承継
同族会社である中小法人の後継者候補は、現経営者の「親族」か「親族以外の第三者」に大別できます。
親族以外の第三者として誰を後継候補にするのも自由です。しかし通常は、その会社に長く勤めた従業員、いわゆる「番頭格」の社員を選ぶことが多いでしょう。
後継候補選びで基準になるのは、以下の要素です。
- 事業を遂行する上での能力
- 他の社員や取引先との円滑な関係を構築できる人間力の有無
ただこうした基準は、社内事情や会社をとりまく環境を考慮して、現経営者の方が考えることです。単純に第三者が指南はできません。
ひとつ言えることは、親族から後継者候補を選ぶ場合でも、親族以外の第三者から選ぶ場合でも、様々な意味で「信頼できる人物がいるかどうか」が大きなポイントになる、ということです。
まとめ
中小企業における事業承継について第1回記事である今回は、最初に考えるべき、事業承継者の選定をテーマに解説しました。
事業承継においては、「誰に事業を引き継ぐのか」を、すべての起点として決定しなくてはなりません。また事業承継者を決定する時の注意事項や、引継ぎ時の法律的・制度的手続きについても解説しています。
事業承継をお考えの方には、とても役立つ内容です。次回以降の記事では「自社株をどのように引き継ぐか」について、徹底的に詳しくご説明します。こちらもぜひ、あわせてお読みください。
お電話でのご相談
上記フリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。
(スマートフォンの方はアイコンをタップして発信)
メールでのご相談
お悩み・ご状況をお知らせください。
担当者より平日の2営業日以内に連絡いたします。
オンラインでの面談
オンラインツールを使用した面談も可能です。
まずはこちらからお問い合わせください。


