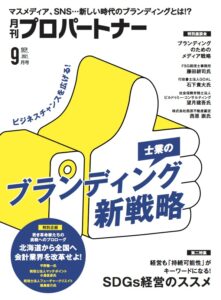相続手続きの期限を早い順に解説!

人が亡くなると、その瞬間から相続の手続きが始まります。
期限内に終わらせないと法律違反になるものもあるので、注意しなくてはなりません。期限を守らないと、金銭的に大きな損をこうむる場合もあります。
法律に反したり、損したりすることがないよう、どうか相続手続きは決まった期限内に済ませてください。とはいえ相続手続きにはどんなものがあるのか、どの手続がいつまでなのか、といったことは、やったことがない方にはよくわかりませんよね。
そこでこの記事では、相続で必要となる手続きを締切が早い順にまとめました。
1.相続で必要になる13の期限あり手続き
相続の手続きで期限が決まっているものを早い順にまとめました。
| 手続き種類 | 期限 |
| 死亡診断書 | 死後すぐ |
| 死亡届 | 7日 |
| 年金の手続き | 10〜14日 |
| 健康保険・介護保険の手続き | 14日 |
| 相続放棄 | 3ヶ月※1 |
| 限定承認 | 3ヶ月※2 |
| 準確定申告 | 4ヶ月 |
| 相続税の申告 | 10ヶ月 |
| 申告した相続税の納付 | 10ヶ月 |
| 遺留分侵害請求 | 1年 |
| 生命保険金の請求 | 3年 |
| 相続不動産の登記 | 3年※3 |
| 相続税の還付請求 | 5年10ヶ月 |
【参考】
※1 相続放棄の期限
※2 限定承認の期限
原則として 相続放棄・限定承認の期限は3ヶ月です。ただし熟慮期間の伸長制度を使うことで、3ヶ月または1年延長が認められるケースがあります。
【根拠となる法律】
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
出典引用:民法第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
【参考2】
※3 相続不動産の登記
2021年に相続不動産についての改正法案が国会で可決されました。2024年までに法律が施行されると、相続で不動産を取得したら3年以内の相続登記が必須となります。
出展:法務省民事局資料
http://www.moj.go.jp/content/001347356.pdf
それでは、各手続きを順番に解説します。
1-1.死亡診断書は死後すぐ
死亡診断書は、死後すぐに取得する必要があります。死亡診断書は医師が作ります。
1-2.死亡届は死後7日以内
死亡届は、死後7日以内に役所に提出する必要があります。死亡届の用紙はは死亡診断書と同じです。「え?何それ?」と思われるかもしれませんね。医師が作成した死亡診断書の左ページが死亡届になっております。死亡診断書を受け取ったら、死亡届の欄に必要事項を記入して提出します。
1-3.年金受給停止の手続きは10〜14日以内
亡くなった方が年金を受給していた場合は、受給停止の手続きをします。
・厚生年金の受給停止→10日以内
・国民年金の受給停止→14日以内
手続き先は年金事務所または年金相談窓口です。
1-4.健康保険・介護保険の資格喪失手続きは14日以内
健康保険・介護保険の資格喪失手続きは、死後14日以内に保険の管理団体に届け出ます。
・国民健康保険に加入しているなら→市区町村村役場
・組合けんぽ、協会けんぽなどの被用者保険に加入しているなら→勤務先か健康保険組合
1-5.相続放棄は3ヶ月以内
相続放棄の手続きは、相続が始まったことを知った日から、3ヶ月以内に済ませなくてはなりません。3ヶ月が経過した後では、相続放棄は認められないのです。
相続放棄ができないと起きる問題は、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうことです。相続放棄を選べば、全ての財産を相続しないことになります。その結果マイナスの財産も引き継がずに済むのです。
1-6.限定承認は3ヶ月以内
限定承認の手続きは、相続が始まったことを知った日から、3ヶ月以内に済ませなくてはなりません。3ヶ月以内という点は相続放棄と同じです。
限定承認とはマイナスの財産とプラスの財産がある場合に、プラス財産分の資金を用意できれば、マイナスの財産を引き継がずプラス財産のみ引き継げる、という仕組みです。
ちょっとややこしいですね。限定承認は、相続財産にプラスのものマイナスのもの両方含まれていて、どちらが多いかわからないときに有効な相続の方法です。
限定承認については、こちらの遺産相続【全手続きの流れ】はこれだけ見れば丸わかり 記事で、具体例を出して解説しています。詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
1-7.準確定申告は4ヶ月以内
準確定申告は、亡くなった方の所得に対する確定申告です。準確定申告は、死後4ヶ月以内に済ませなくてはなりません。
通常の確定申告の場合は、1年分を翌年の2月〜3月に行います。しかし亡くなった方の確定申告である準確定申告の締切は、亡くなってから4ヶ月以内です。
準確定申告の締切は、人によって異なりますし、一般的な確定申告より早まるので要注意です。
準確定申告についてこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にお読みください。
1-8.相続税の申告は10ヶ月以内
亡くなった方の財産を引き継いだ相続人は、相続発生後10ヶ月以内に相続税を申告しなくてはなりません。
注意する点は、特例を適用した結果、相続税額が0円となる場合も申告は必要ということです。(ただし、相続財産に対する課税額の合計が基礎控除以下のために相続税が0円になった場合は、申告の必要はありません。)
1-9.申告した相続税の納付は10ヶ月以内
申告した相続税は、相続発生後10ヶ月以内に納付しなくてはなりません。
・相続税の申告
・相続税の納付
つまり申告と納付の期限は同時です。したがって、申告の結果納税が発生する場合は特に注意が必要です。期限を守らない場合は延滞税が課せられる可能性があり、余計な費用がかかります。
期限間近なのに、相続税の申告・納税手続きが手つかずで途方にくれている方は、ぜひ相続専門の税理士にご相談ください。
税理士法人ともには、申告まで時間がない方のご相談を承ります。ともにへのご相談はこちらからどうぞ。
1-10.相続税の還付請求は5年10ヶ月以内
相続税を払い過ぎている場合は、相続税の還付請求ができます。還付請求が認めらると、払いすぎた税金が戻ってきます。
相続税の還付請求の期限は5年10ヶ月以内。正確には相続の開始を知った日の翌日から5年10ヶ月以内が期限となります。
還付請求のご相談は税理士法人ともにでも承っております。「もしかすると私も相続税を払いすぎているかも?」と疑わしく思われるなら、ぜひご相談ください。
迷っている間に5年10ヶ月の期限を迎えてしまわないよう、お早めにご相談ください。
1-11.遺留分侵害請求は1年以内
遺留分侵害請求の期限は、死後1年以内です。遺留分侵害請求とは、法定相続人に認められている相続財産の取り分を守る権利のこと。
法定相続人には相続順位があり、順位ごとに相続できる財産割合が法律で決まっています。
相続で受け取る金額が、決められた割合より少ない場合、遺留分侵害請求で取りもどすことができます。その遺留分侵害請求の期限が亡くなってから1年以内なのです。
1-12.生命保険金の請求は3年以内
亡くなった方が生命保険(死亡時に保険金が出る保険)に加入していた場合は、保険会社に保険金支払いの請求をします。この生命保険金の請求期限は、亡くなってから3年以内です。
1-13.相続不動産の登記は3年以内(2023年度から)
不動産を相続する場合は、登記してあるその不動産の名義を書き換えます。これを不動産登記と呼びます。不動産登記は、その不動産を取得すると知った日から3年以内に済ませましょう。
2021年現在、相続不動産の登記はまだ義務ではありません。しかし2023年度までに相続不動産の登記は必須となります。
しかし義務化前であっても、登記は早めに済ませることをおすすめします。なぜなら不動産を登記しないとできないことがあるからです。たとえば相続不動産の売却は登記しておかないとできません。
2.相続手続きで期限がないもの
相続手続きの中には、期限の制定がないものもあります。しかし以下2つの手続きは、やっておかないと他の期限あり手続きが進みません。
・遺言書の検認
・遺産分割協議
早い段階で終わらせるべき2つの手続きを解説します。
2-1.遺言書の検認
遺言書の検認は、すべての遺産相続手続のスタートになるものです。亡くなった方が作った自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所で検認してもらわないと有効になりません。期限が決まっていなくても、相続が始まり遺言書があるのなら、すぐに検認を実行しましょう。
2-2.遺産分割協議
遺産分割協議についても、法律では期限を決めていません。しかし、遺言書がなく相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をして、相続財産をどのように分けるか決めなければなりません。
相続財産の分け方が決まらないと、その後の相続税の申告ができません。申出により遺産分割協議を相続税の申告後に行うこともできますが、協議が必要なことは変わりません。
遺産分割協議も、相続手続きの早い段階で終わらせましょう。
まとめ
相続手続きの期限について、締切が早い順に解説しました。
相続に必要な手続きの期限は、死後すぐに行うものから、3年以内までと幅が広いです。しかし期限に遅れると、過料や延滞料を請求されることがあります。また手続きの遅れにより、大きな借金を背負うといった経済的損失を被ることもあります。
死後の相続手続きは、期限を守って、確実に終わらせていきましょう。
お電話でのご相談
上記フリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。
(スマートフォンの方はアイコンをタップして発信)
メールでのご相談
お悩み・ご状況をお知らせください。
担当者より平日の2営業日以内に連絡いたします。
オンラインでの面談
オンラインツールを使用した面談も可能です。
まずはこちらからお問い合わせください。